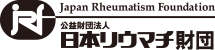リウマチに関連する病気
リウマチ性多発筋痛症
- ①リウマチ性多発筋痛症とは?<病気の概念>
-
リウマチ性多発筋痛症(Polymyalgia rheumatica :PMRと略されます)は、発熱とくびの後ろ、肩甲帯部、腰臀部などの筋肉痛と朝のこわばり、身体に力が入りにくい等を特徴的な症状とし、決してまれではない病気で、血液でCRP高値、赤沈(血沈)亢進などの炎症反応を認める比較的高齢者に好発し、現在のところ原因不明な病気です。治療には副腎皮質ステロイドステロイドホルモン(ステロイド)が劇的な効果があります。日本人の場合は、再発・再燃が多いとされています。また、日本人では欧米人より少ないですが、時に巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)を併発することがあります。
- ②この病気はどのような人に発病するのですか?<男女比・発病年齢>どのくらいの患者さんがいるのですか?<有病者数、発病率>
-
リウマチ性多発筋痛症は、一般には50歳以上の中高年に発病し、発病年齢は年齢とともに増加し、70~80歳にピークがあり、高齢者に多い病気です。もちろん、比較的若年にも発病しますが、小児には発症しません。男女比は1:2~3と女性に多いようです。関節リウマチの十分の一以下と考えられます。この病気の患者さんの数は、白色人種、特に北欧では多く人口10万人あたりの年間発病数は50歳以上で60~80人、アメリカでも、人口10万人で18.7~68.3 人、とくに50歳以上の人口10万人に対しては年間50人ほど発病するとされています。日本人は50歳以上の人口10万人あたり約20人と、欧米人よりも少ないとされております。また、日本の有病率は臨床医の印象として、人口の0.1%程度とされ、決してまれな病気ということではありません。
- ③この病気の原因はわかっているのですか?<病因>
-
はっきりした病因はわかっていませんが、病気のグループとしてはリウマチ・膠原病に属します。したがって、この病気には地域・人種差が大きいことから遺伝的要因を背景に免疫の異常による急性炎症が病気の成り立ちに重要だろうと考えられています。
- ④この病気ではどのような症状がありますか?<症状>
-
リウマチ性多発筋痛症では、発病が比較的急激で2週間以内に典型的症状が揃うことが多いです。全身の症状、筋肉の症状、関節の症状の3つが主な症状です。全身症状としては、38℃代までの発熱(80%)、食欲不振(60%)、体重減少(50%)、全身倦怠感(30%)、抑うつ症状(30%)などがみられます。筋肉の症状としては、両側の肩(70-95%)、くび、臀部(50-70%)、腰部、大腿などに痛みやこわばりがでます。しかし一般に厳密な意味での筋力の低下はありませんが、筋肉の強いこわばりと痛みで手足が固まって力が入りにくく、手足を動かせないと自覚されます。また手足の躯幹部を軽く握られても筋肉に痛みを感じます。これら症状は朝の起床時が最も強く、床からなかなか出れない状態になります。しかし、午後にはこれら症状がある程度軽快することが特徴です。
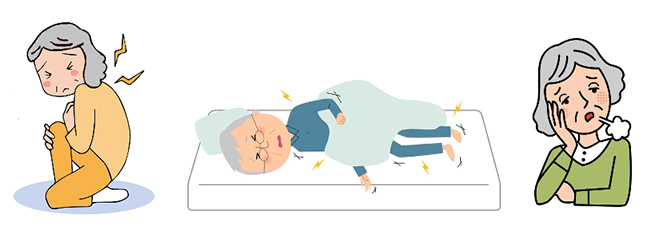
その他に大きな関節を中心にした関節の痛み、不眠などを伴います。 また、巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)が日本人で高々20%程度に合併します。このような時は、側頭部を中心とした頭痛、側頭部の動脈の蛇行や拍動、触れると痛みを伴ったり、視力の低下、食物を食べていると顎が痛くなったり、噛めなくなるような症状(顎跛行)がみられることがあります。
- ⑤この病気はどのように診断するのですか? <診断>
-
この病気の症状は類似の様々な他の病気にも見られること、検査で特にこの病気で特別に認められるものがないことから、診断は簡単ではありません。診断は年齢や病気の発現の仕方や症状の内容と炎症所見の存在を示す、赤沈の亢進やCRPの上昇、時には血中MMP-3の治療前の上昇などを参考にして、提案されている診断基準等に照らして行われています。診断基準としては、Birdらの1979年基準が、かつては用いられていましたが、最近では比較的この病気に特徴的な画像検査として、肩、股関節部のエコー(超音波)検査が取り入れられた欧州リウマチ学会(EULAR)・米国リウマチ学会(ACR)合同による2012年分類予備基準がよく用いられます。しかし、確定診断には同様の症状や炎症所見(赤沈の亢進やCRPの上昇)を呈する関節リウマチなどどの類似の病気を十分に除外する必要があります。
一方、リウマチ性多発筋痛症に巨細胞性動脈炎の併存が疑われる場合は、造影検査を含む各種画像検査(超音波検査、MRI,PET-CT画像など)、眼科、歯科・口腔外科などでの精査も行われますが、最終的に巨細胞性動脈炎の診断の確定に、頭皮の浅側頭動脈の生検が必要なることもあります。
- ⑥この病気にはどのような治療法が行われますか?<治療>
-
リウマチ性多発筋痛症には、ステロイドが劇的な効果を示します。患者さんごとの重症度、合併症等を考慮して、中等量までのステロイド(プレドニン12.5~25mg/日)が推奨されています。多くの場合薬剤服用の1-3日以内に効果がみられます。しかし、短期間で効果があっても、一定期間(2~3週)の初期服用量を継続し、急性期の炎症を完全に鎮静化する必要がり、症状や臨床検査の炎症所見(赤沈やCRP)の推移をみて、全身の炎症を抑えるためにステロイドが減量されますが、早期の減量は病気の再発を起こしやすいとされており、特に日本人は欧米人に比べて再発しやすいので、減量は慎重に行うのが一般的です。ステロイド服用で劇的効果があるからと言って、簡単に減量したり、中止してしまうと、再び病気が悪くなりますので、必ず医師の指示通りの服用をすることが大切です。本症に巨細胞性動脈炎が合併した場合は、より高用量のステロイドが必要となります。
ステロイドの減量や中止で再発をたびたび繰り返す難治例の場合は、ステロイドに抗リウマチ薬であるメソトレキサートを併用されることもありますが、確実な効果はまだ限定的です。さらに、最近では難治例に強い持続的炎症を抑える目的で生物学的製剤、特にIL-6阻害薬が使用されてきており、有効性を示す報告が増えてきています。しかし、本邦ではIL-6阻害薬は、この病気に対する公的保険の適応はありませんが、合併する巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)にIL-6阻害薬は認められています。

- ⑦この病気の生活上の注意は何かありますか?<生活上の注意>
-
巨細胞性動脈炎の合併が無ければ基本的には治療後の見通し(予後)は比較的良好で、筋肉や関節破壊を来たすことはなく、臓器障害を来たすこともありません。かつて、この病気とがんを含む悪性腫瘍が併存しやすいとの報告もありましたが、最近では同年代の一般の方々と変わらないとされています。しかし、患者さんの年齢を考えれば、この病気の診断時に悪性腫瘍のスクリーニングは必要でしょう。したがって、この病気そのものによって死亡率は高まりませんが、ステロイドによる副作用(感染症、糖尿病、高血圧、脂質異常症、骨粗しょう症、緑内障、白内障、筋肉量低下など)の影響を最小限にする予防、特にステロイド性骨骨粗しょう症への対策が必要です。また、経過中に巨細胞性動脈炎の合併がないかを注意深く観察する必要もあります。しかし、病気そのもののために特別に気をつけることはありません。
【情報更新】令和4年8月