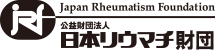ACR 2024
(五十音順)
京都府立医科大学大学院医学研究科 免疫内科学 金下 峻也
この度、令和6年度日本リウマチ財団国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成を受け、アメリカリウマチ学会2024に参加する機会を頂きました。本学会では、ポスターセッションにおいて2つの研究成果を発表いたしました。これらの研究は、2022年から2024年にかけて、アメリカのカリフォルニア州立大学サンディエゴ校の公衆衛生学修士課程で取り組んだ臨床研究です。修士過程で疫学を選考していたので、主に臨床データを用いた疫学研究となります。
1つ目の研究は、PET-CTを撮影したリウマチ疾患患者のデータを用い、痛風患者とコントロール群を比較した研究です。腹部皮下脂肪および腹部内臓脂肪のSUV値をPET-CTを用いて測定し、その差を評価した結果、痛風患者では腹部皮下脂肪・内臓脂肪いずれにおいてもSUV値が高いことが示されました。また、この値が高い患者において、慢性腎臓病の進行リスクが高いことが示唆されました。今年のアメリカリウマチ学会では、GLP-1受容体作動薬という肥満治療薬が、肥満に対してだけでなく変形性関節症、脂肪肝、慢性腎臓病など様々な疾患に有効性がある可能性が報告されていました。私の研究結果も、痛風患者の慢性腎臓病進行という現時点で有効な治療法が明らかになっていない病態が、これらの薬剤により脂肪炎症を制御し、治療の病態解明の手がかりとなる研究と考えております。
もう1つの研究は、MotherToBaby Studyという米国・カナダにおける膠原病合併妊娠患者を対象とした大規模コホートデータを用い、COVID-19ワクチンの短期副作用頻度を評価しました。結果として、膠原病を合併していても短期副作用頻度に大きな差は示されませんでした。しかし、機能的寛解スコア(HAQ-DI)が高い患者集団では、1回目のワクチン接種で発熱や頭痛などの全身的な副作用頻度がやや高い傾向が見られました。また、薬剤による副作用頻度についても解析したところ、ステロイドや抗リウマチ薬の使用状況によって異なる傾向が確認されました。特に、ステロイドの使用がなく抗リウマチ薬のみを使用している病状が安定した患者では副作用頻度が低い傾向が見られました。この結果は、膠原病合併妊娠患者においてワクチン接種に対する過度の懸念が不要であることを示唆するとともに、可能であれば病状が安定した状態でワクチン接種することで副作用頻度が低減する可能性があることを示しています。ワクチン忌避が公衆衛生上の課題となる中、このような情報はワクチン接種を躊躇する膠原病合併妊娠患者にとって貴重な知見となると考えられます。
ポスターセッションでは、多くの研究者に関心を持っていただき、世界各国のリウマチ専門医と意見交換する機会を得ることができ、大変刺激を受けました。また、自身の発表だけでなく、世界中の一流研究者によるレクチャーから最新のリウマチ・膠原病に関する研究や情報を学び、日々の診療や次の研究に活用したいです。
近年の円安の影響もあり、国際学会への参加費用が高騰し、日本人研究者の参加が難しくなっている状況です。開催地がワシントンという地理的条件もあり、日本人研究者の参加数が少ない印象を受けました。そのような中で、海外国際学会参加への助成制度は、参加が難しい研究者にとって貴重な機会を提供するものです。このような支援をいただけたことを厚く御礼申し上げます。
北海道大学大学院医学院・医学研究院 免疫・代謝内科学教室 竹山 脩平
この度令和6年度日本リウマチ財団国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成を頂き,誠にありがとうございました。ご評価いただきました選考委員の方々をはじめ財団関係者の皆様,ご推薦頂きました渥美達也教授にはこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
本助成を受け、令和6年11月14日から19日にアメリカ合衆国、ワシントンD.C.において開催された2024年アメリカリウマチ学会総会 (ACR Convergence 2024) に出席し、研究内容を口演発表させて頂きました。
現在私は全身性エリテマトーデスの重要臓器病変である神経精神ループス (NPSLE) の病態解明及び新規治療の開発を中心に、基礎研究および臨床研究に従事しております。NPSLEの病態形成の全容は明らかになっておりませんが、近年ミクログリアの重要性が注目されておりました。我々は疾患モデルマウスであるMRL/lprマウスについて、同マウスから分離したミクログリアが異常活性化し、同マウスは異常行動を呈することを示しておりました。今回さらに我々はMRL/lprマウスから分離したミクログリアにおいてRNA sequencing解析を行い、Phosphodiesterase 1b (PDE1B)という分子に着目しました。続いてPde1b遺伝子をミクログリア特異的に欠損させたコンディショナルノックアウトマウスを作成し、同マウスおよびMRL/lprマウスにおいて、そのミクログリアの機能解析ならびに行動解析による異常行動の評価を行いました。その結果、PDE1Bの遺伝子欠損ならびに薬物的阻害によりミクログリアの活性化が抑制され、行動異常が改善することを示しました。PDE1Bはミクログリアの異常活性化を通じてNPSLEの病態形成に関与していることが示唆され、新規治療ターゲットになり得ると考えられました。
会場にはアメリカ合衆国をはじめ各国の研究者が参加しており、重要な観点からの質問を通じ、本研究の今後の検討課題について考察を深めることができ、大変有意義な時間となりました。また、私自身の発表技術や語学力が向上し、最新の研究内容に直接触れることができ、研究活動のモチベーションを更に高めることができました。自身の所属研究室にこの経験を還元するだけでなく、自己免疫疾患における基礎研究のさらなる発展に貢献したいと考えております。
最後になりますが、このような貴重な機会に関しまして、貴財団より温かいご支援を頂きましたことに心より御礼申し上げます。
京都大学大学院 医学研究科 臨床免疫学 中山 洋一
この度は、令和6年度日本リウマチ財団国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成を賜り、誠にありがとうございました。ご評価いただきました選考委員の先生方をはじめ、財団関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
いただいた助成金のおかげで、2024年11月16日から11月19日にかけてアメリカ・ワシントンDCで開催されたアメリカリウマチ学会年次学術集会に参加し、研究成果を発表する機会を得ることができました。今回の学会では、3件の演題発表を行い、いずれの発表においても海外の研究者と活発な議論を交わすことができました。
1つ目の演題では、自己免疫性関節炎モデルマウスを用いた核内受容体を標的とした治療効果の検討について報告しました。核内受容体のアゴニストを使用し、その機能を増強することで、T細胞活性化の抑制とIL-6シグナル伝達の抑制を促し、関節炎の症状を軽減する研究内容です。同じ標的を別疾患で研究している海外の研究者と意見を交換する中で、今後の研究の方向性を見出すことができました。
2つ目の演題では、関節リウマチにおける生物学的製剤およびJAK阻害薬の治療反応性を罹病期間が短い群と長い群で比較した臨床研究について発表しました。臨床医の参加が多い学会であるため注目度が高く、多くの先生方からご質問をいただきました。特にドイツの著名なリウマチ学教授からご質問や助言をいただき、論文化の際にはさらに研究内容を洗練させることができると考えています。
3つ目の演題では、ANCA関連血管炎における鼻腔細菌叢の研究について報告しました。この分野は類似研究が少ないため、興味深く聞いていただき、多数のご質問をいただきました。現場での反響を実感したことで、自信を持って研究をさらに進めていきたいと感じています。
学会期間中は、海外の研究者による口演やポスター発表を通じて、リウマチ学の最新の潮流を基礎医学と臨床医学の両面から把握する貴重な機会となりました。
最後に、貴財団からのご支援は、経済的にも心理的にも大きな支えとなり、非常に有意義な国際学会参加を実現することができました。改めて厚く御礼申し上げます。